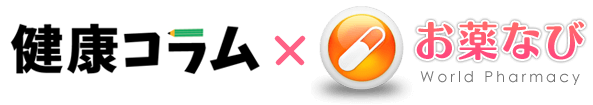お酒と美肌の関係

お酒で美肌になるって聞いたことはありませんか?
そして、お酒で肌が荒れるって聞いたことはありませんか?
お酒に関しては、様々な逸話があるかと思います。
「酒は百薬の長」「お酒は百害あって一利なし」このようにどちらの場合でもお酒が出てくるんですね。
では実際にお酒は良いものなんでしょうか?悪いものなんでしょうか?
ズバリお酒は両方の性質を持っているんです!
それはお肌にも言えることで、お酒によって美肌にもなりますし、肌荒れの原因にもなるんです。
ではそんなお酒のメリット、デメリットを確認してみましょう。
お酒のメリット
お酒を飲むと血行が良くなり、そのおかげで様々効果を得ることが出来ます。また、お酒はストレスなどを緩和する作用があります。ただし、このお酒のメリットを得るには飲む量が適量であることが重要です。
この適量とは一般的に血中アルコール濃度が0.02%と言われています。
日本酒なら1合(180ml)、ビールなら500ml缶1本といった感じです。
ただ、アルコールに関しては、強い、強くないといった個人差や、女性は体内の水分量が少なく、女性ホルモンの影響でお酒に弱いといった傾向があります。
お酒が肌にいい!ということを知っていたとしてもこの適量を守ることが出来なければ大変なことになってしまいます。公益社団法人アルコール健康医学協会が発表しているお酒を飲むメリットとして、お酒を適量飲んでいる人は飲んでいない人よりも長生きをするというデータがあります。
これはいかにお酒を適量飲むことが人体に対していい影響を与えているかという証拠になります。
その根拠として1981年にイギリスのマーモット博士が発表した「飲酒と死亡率のJカーブ効果」という疫学調査では飲み始めてからリスクが下がっていき、ある程度を超えるとリスクが上がっていくという結果になっています。
これは、アルコールの虚血性心臓病(心筋梗塞、狭心症など)に対する予防効果が要因と考えられています。アルコールが善玉コレステロールの量を増やし、悪玉コレステロールを抑えることで心臓病を予防するとされています。
そして、このラインより下の状態が適度な飲酒ということになります。
逆に飲み続ければ続けるほど死亡のリスクが上がっていくという結果になっています。
やはり、飲酒をするには適量を守るということが重要だということがわかりますね。
美肌にはこのお酒!
お酒を適量飲む分には健康にとてもいいことが分かったかと思います。
では、お肌には良い効果があるのでしょうか?
お肌にいいお酒をご紹介致します。
エイジングケア効果を期待するなら、どのお酒を選べばいいのかを見ていきたいと思います。
| お肌を若々しくする赤ワイン |
健康や美容にいいお酒の代表として有名なのがワインかと思います。 よく女優や、セレブも好んで飲んでいるイメージがあるのではないでしょうか? 赤ワインにほ豊富に栄養素が含まれていて、アントシアニンやタンニン、カテキンやレスベラトロールなど、多くのポリフェノールが含まれています。 ポリフェノールにはビタミンやミネラルが豊富に含まれていて、お肌に元気を与えます。 |
|---|---|
| 腸内環境も整える白ワイン |
白ワインにも赤ワインほどではないのですがポリフェノールが含まれています。 なので、ポリフェノールの効果も期待できますが、白ワインには乳酸をはじめとする有機酸が含まれていて、腸内環境を改善する働きがあります。 腸内環境が悪いと、肌荒れの原因になってしまうのですが、白ワインは飲むことで腸内環境に作用をし、腸内環境を整えることで、肌荒れを防ぎ、お肌のキレイに整えてくれます。 |
| 栄養が豊富なビール |
ビールにも美肌の作用のある栄養素がたくさん含まれています。 ビールの原材料にはホップが含まれています。ホップにはアンチエイジングには欠かせない抗酸化作用や、生活習慣病のリスクの低下などの効果が期待できます。 その他美肌の元となるビタミンB群、葉酸、パントテン酸、カリウムなど豊富に含み、必須アミノ酸もバランスよく含まれています。 注意点としてはビールには利尿作用があるので飲み過ぎると水分を体外に排出してしまうので、乾燥肌などになってしまいます。 また、ビールは冷やして飲む方が多いかとは思いますが、冷たいものを飲み過ぎると身体を冷やしてしまって代謝を下げてしまう原因にもなってしまうので注意しましょう。 |
| 旨味成分がお肌にいい日本酒 |
日本酒にも様々な成分が含まれていますが、その中でお肌にいい成分は【旨味】です。この旨味成分は有機酸であるコハク酸やアミノ酸です。 そして、このアミノ酸に含まれている「セリン」が角質内の水分や油分を保持し、肌のバリア機能を強める働きがあるのです。 また、シミの原因となるメラニンの生成を抑える働きがあります。 |
お酒のデメリット
お酒がお肌にいい成分を大量に含んでいることはわかったかた思います。
そんなお酒もお肌に悪い場合があります。
それは飲み過ぎた時です。
基本的にはお肌にいいのですが、飲み過ぎるとお肌に悪影響がでてしまうのです。
| 飲み過ぎるとなる乾燥肌 |
お酒を飲んだ後に体内ではアルコールを分解するために大量の水分とビタミンB群が消費されます。 また、トイレの回数が増える人も多くいらっしゃると思います。 お酒を飲み過ぎてしまうと、消費する水分も多くなってしまい、軽い脱水症状のような状態になります。 お酒を飲んだ後、のどが渇くのはこのため。 乾燥肌は小じわをはじめ、様々な肌悩みの原因になってしまいます。 |
|---|---|
| セロトニン不足でお肌 |
アルコールによってビタミンBが大量に消費されてしまうことで、セロトニンが生成出来なくなってしまい、様々な肌に悪い効果が出てきます。 セロトニンは睡眠に必要なメラトニンの生成にかかわってきます。 メラトニンは自律神経に作用をして、脳を睡眠へと導く役割があります。 セロトニンが不足すると、メラトニンが不足をし、睡眠障害になってしまうのです。 また、セロトニンは満腹中枢を刺激するホルモンでもあります。 |
| 活性酸素がお肌を老化させる |
アルコールは肝臓で分解されます。 その肝臓で分解される時に活性酸素を生み出します。 この活性酸素によりお肌が酸化して、老化していってしまうのです。 アンチエイジングの真逆ですね。 このようにお酒にはメリットとデメリットがあることがわかったかと思います。 |
お酒が好きなひとの為に
やっぱり多く飲みたいそんな人の為に!
| 水分を多く取る |
アルコールを分解するには大量の水分が必要になります。 なので、お酒を飲んだ以上に水分を取りましょう。 そうすることで、脱水状態を防ぎ、乾燥肌の予防になります。 |
|---|---|
| おつまみを工夫する |
睡眠不足などの原因となるセロトニン不足を防ぐ為にはビタミンB群を摂取しましょう。 豆類、木の実、牛肉、豚肉、オレンジなど、ビタミンB群が豊富なおつまみを選びましょう。 特に豆や木の実は手軽に食べることが出来るので、お酒のお供にぴったりです! |
お酒と上手に付き合うには
お酒は飲み方によってはお肌にいいこともあれば、悪いこともあります。
自分の飲める量をしっかりと把握して飲み過ぎないことが第一です。
せっかくお肌にいい成分がたっぷり入っているので、しっかりと美容に使っちゃいましょう!
更新日時:2019年06月25日