- 新規登録
 お気に入り
お気に入り お知らせ
お知らせ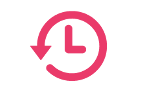 注文履歴
注文履歴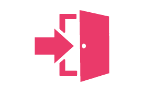 ログイン
ログイン-
 0
¥
0
買物カゴ
0
¥
0
買物カゴ
個人輸入医薬品をお探しの際は薬機法準拠のため医薬品名を正確に入力して下さい。
![]() お知らせ
お知らせ
![]() 注文履歴
注文履歴
![]() ログイン
ログイン
個人輸入医薬品をお探しの際は薬機法準拠のため医薬品名を正確に入力して下さい。
1位
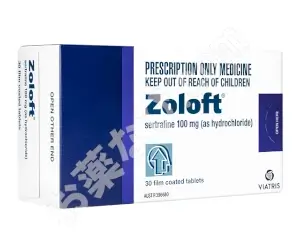 ジェイゾロフト
ジェイゾロフト
1錠:72円~
 (132件)
(132件)
2位
 パキシルジェネリック
パキシルジェネリック
1錠:81円~
 (86件)
(86件)
3位
 レクサプロ・ジェネリック
レクサプロ・ジェネリック
1錠:31円~
 (141件)
(141件)
4位
 デュゼラ
デュゼラ
1錠:44円~
 (89件)
(89件)
5位
 ルボックス・ジェネリック
ルボックス・ジェネリック
1錠:90円~
 (11件)
(11件)
6位
 イフェクサー・ジェネリック
イフェクサー・ジェネリック
1錠:66円~
 (71件)
(71件)
7位
 プロザック・ジェネリック
プロザック・ジェネリック
1錠:27円~
 (17件)
(17件)
8位
 レメロン・ジェネリック
レメロン・ジェネリック
1錠:98円~
 (62件)
(62件)
| 商品名 | ピルカッター |
|---|---|
| 成分 | なし |
| 効果 | 錠剤カット |
| 副作用 | なし |
| 使い方 | 錠剤をセットしてケースを畳むように閉じる |
| 製造元 | 発送国により異なる |
| 商品名 | セドキシル |
|---|---|
| 成分 | メキサゾラム |
| 効果 | 不安障害やうつ病の改善 |
| 副作用 | 眠気、ふらつき、倦怠感、脱力感など |
| 飲み方 | 1日1.5~3mgを、3回に分けて服用 |
| 製造元 | Bial |
| 商品名 | リカブ(リーマスジェネリック) |
|---|---|
| 成分 | 炭酸リチウム |
| 効果 | 躁状態改善 |
| 副作用 | めまい、ねむけ、吐き気など |
| 飲み方 | 1日400~600mgを2、3回に分けて服用 |
| 製造元 | トレントファーマ |
| 商品名 | ジェイゾロフト |
|---|---|
| 成分 | 塩酸セルトラリン |
| 効果 | うつ病、パニック障害、外傷後ストレス障害などの改善 |
| 副作用 | 睡眠障害、頭痛、動悸、便秘、発疹など |
| 飲み方 | 1日1回、1回25mg~最大100mgまでを夕食後に服用 |
| 製造元 | ヴィアトリス、ファイザー |
| 注意 | 発送時期によりメーカー,パッケージが異なります。あらかじめご了承ください。 |
| 商品名 | ルボックス・ジェネリック |
|---|---|
| 成分 | フルボキサミンマレイン酸塩 |
| 効果 | うつ病、強迫性障害、社交不安障害(あがり症)などの改善 |
| 副作用 | めまい、動悸、発疹、貧血、口喝など |
| 飲み方 | 毎日決まった時間に、50mg~150mgを1日2回に分けて食後に服用 |
| 製造元 | アボット |
| 商品名 | L-チロシン |
|---|---|
| 成分 | L-チロシン/500mg |
| 効果 | うつ症状の改善、集中力UP、白髪予防 |
| 副作用 | 特に報告されていません |
| 飲み方 | 1日に1~3回、1回1錠を目安に飲用して下さい。 |
| 製造元 | Sapphire Healthcare |
| 商品名 | レキサルティ |
|---|---|
| 成分 | ブレクスピプラゾール |
| 効果 | 統合失調症、うつ病・うつ状態 |
| 副作用 | アカシジア、体重増加など |
| 使い方 | 1日1回、1mgから開始 |
| 製造元 | 大塚製薬 |
| 在庫 | 現在1mg欠品中です。 次回3月中旬入荷予定 類似商品は以下をご覧ください。 ・ジェイゾロフト:ジェイゾロフトはうつ病や不安障害の治療薬で、パニック障害などの不安障害などにも効果を期待できます。 ・レクサプロ・ジェネリック:レクサプロ・ジェネリックはシプラ社が開発した、うつ病や社交不安障害の治療薬です。 |
| 商品名 | ブプロバン |
|---|---|
| 成分 | ブプロピオン塩酸塩 |
| 効果 | うつ病改善、禁煙補助 |
| 副作用 | 緊張感、便秘、不眠症、口の渇きなど |
| 飲み方 | うつ病改善の場合は毎朝1錠服用、禁煙補助の場合は1日2回1錠ずつ服用 |
| 製造元 | Healing Pharma |
| 商品名 | デュゼラ |
|---|---|
| 成分 | デュロキセチン塩酸塩 |
| 効果 | うつ病、慢性腰痛症、変形性関節症などの改善 |
| 副作用 | 倦怠感、頭痛、動悸、耳鳴、排尿困難など |
| 飲み方 | 1日1回、20mg~60mgを朝食後に服用 |
| 製造元 | サンファーマ |
| 先発薬 | サインバルタはこちら |
| 在庫 | 現在【30mg】欠品中です。次回入荷時期未定。 |
| 商品名 | イフェクサー・ジェネリック |
|---|---|
| 成分 | ベンラファキシン塩酸塩 |
| 効果 | うつ病改善 |
| 副作用 | 傾眠、悪心、動悸、肝機能検査値異常、γ-GTPの上昇など |
| 飲み方 | 1日1回食後に服用。1回37.5mgより開始し、1日225mgまで増量可。 |
| 製造元 | シプラ |
| パッケージ | ※発送時期によりパッケージが異なる場合がありますが、品質には問題ありません。 |
| 商品名 | パキシルジェネリック |
|---|---|
| 成分 | パロキセチン塩酸塩水和物 |
| 効果 | うつ病、パニック障害、あがり症(社交不安障害)などの改善 |
| 副作用 | めまい、倦怠感、口喝、発汗など |
| 飲み方 | 1日1回夕食後に服用 |
| 製造元 | ザイダスカディラ |
| 商品名 | トリプタノールジェネリック |
|---|---|
| 成分 | アミトリプチリン |
| 効果 | うつ病、夜尿症の改善 |
| 副作用 | 循環器障害、精神神経障害、発疹、蕁麻疹、肝臓機能障害など |
| 飲み方 | うつ病の場合、1日30~75mgを初期用量で服用(最大300mg) 夜尿症の場合、1日10~30mgを就寝前に服用 |
| 製造元 | Teva |
| 在庫 | ※10mg、25mg現在欠品中です。 次回入荷時期未定。 |
| 商品名 | ベネジスXR |
|---|---|
| 成分 | ベンラファキシン塩酸塩 |
| 効果 | うつ病改善 |
| 副作用 | 傾眠、口内乾燥、頭痛、眠気、めまい、動悸など |
| 服用方法 | 1日1回食後に服用。1回37.5mgより開始し最大225mg/1日まで増量可 |
| 製造元 | Egis Pharmaceuticals PLC |
| 商品名 | アモキサン・ジェネリック |
|---|---|
| 成分 | アモキサピン |
| 効果 | うつ病改善 |
| 副作用 | 精神神経障害、精神神経系障害、抗コリン作用、発疹、紅斑など |
| 飲み方 | 毎日決まった時間に、1日25~75mgを1~数回に分けて服用 |
| 製造元 | Consern Pharma |
| 商品名 | ジプレキサ・ジェネリック(オリザ) |
|---|---|
| 成分 | オランザピン |
| 効果 | 統合失調症、双極性障害、うつ病などの症状改善 |
| 副作用 | 傾眠、不眠、めまい、アカシジア、便秘など |
| 飲み方 | 1日1回、水かぬるま湯で分割服用。用量は症状によって異なる |
| 製造元 | インタスファーマ |
| 商品名 | ソリアン |
|---|---|
| 成分 | アミスルプリド |
| 効果 | 統合失調症の治療 |
| 副作用 | 震え、眠気など |
| 飲み方 | 1日50~300mgを服用 |
| 製造元 | サノフィ |
| 使用期限 | 現在発送される商品の使用期限が2026年08月となります為、ご注文に際しては、予めご了承の上、ご注文頂けますようお願いいたします。 |
| 商品名 | テグレトールジェネリック |
|---|---|
| 成分 | カルバマゼピン |
| 効果 | てんかん発作抑制、躁うつ病、三叉神経痛などの症状緩和 |
| 副作用 | 血管炎、血管浮腫、皮膚障害、血液障害、腎臓障害など |
| 飲み方 | てんかん、躁うつ、統合失調症の興奮状態の場合1日200~400mgを初期用量として1~2回に分けて服用し、その後効果が得られるまで徐々に増量。三叉神経痛の場合1日200~400mgを初期用量として数回に分けて服用。 |
| 製造元 | Myfarma ilac San |
| 商品名 | サミー(SAM-e) |
|---|---|
| 成分 | S-アデノシルメチオニン(SAM-e) |
| 効果 | うつ病、肝機能などの改善 |
| 副作用 | 特に報告されていません |
| 飲み方 | 1日2錠を2~6回摂取 |
| 製造元 | Life Extension |
| パッケージ | 発送時期により、メーカーパッケージが異なります。 |
| 商品名 | トレドミン・ジェネリック |
|---|---|
| 成分 | ミルナシプラン塩酸塩 |
| 効果 | うつ病改善 |
| 副作用 | 頻脈、めまい、発疹、口渇、γ-GTPの上昇など |
| 飲み方 | 1日2~3回に分けて食後に服用。1回25mgより開始し、最大1日100mgまで増量可 |
| 製造元 | Consern Pharma |
| 商品名 | トフラニール |
|---|---|
| 成分 | イミプラミン |
| 効果 | うつ病、遺尿症の改善 |
| 副作用 | 循環器障害、精神神経障害、抗コリン作用、発疹、肝臓機能障害など |
| 飲み方 | うつ病の場合、1日30~75mgを初期用量で服用(最大300mg) 遺尿症の場合、30~50mgを1日1~2回に分けてに服用 |
| 製造元 | Assos |
| 商品名 | アミトン |
|---|---|
| 成分 | アミトリプチリン |
| 効果 | 片頭痛予防、うつ病、夜尿症、末梢性神経障害性疼痛の治療 |
| 副作用 | 眠気、口の渇き、発疹、食欲不振など |
| 飲み方 | ■うつ病 1日30~75mgを数回に分けて服用する ■夜尿症 1日10~30mgを就寝前に服用 ■末梢性神経障害性疼痛 初期は1日10mgを服用する |
| 製造元 | インタスファーマ |
| 商品名 | セルトラリン |
|---|---|
| 成分 | セルトラリン |
| 効果 | うつ病、パニック障害、外傷後ストレス障害の治療 |
| 副作用 | 下痢、吐き気、食欲減退など |
| 飲み方 | 1日1回25~100mgを服用 |
| 製造元 | Sanovel |
| 商品名 | コントミン・ジェネリック |
|---|---|
| 成分 | クロルプロマジン塩酸塩 |
| 効果 | 統合失調症、不安障害、うつ病などの改善 |
| 副作用 | 血圧降下、頻脈、食欲不振、悪心、嘔吐など |
| 飲み方 | 1日30mg~100mg、精神科領域においては1日50mg~450mgを分割して水かぬるま湯で服用 |
| 製造元 | DD Pharma |
| パッケージ | 発送時期により、メーカーパッケージが異なります。 |
| 商品名 | シタロプラム |
|---|---|
| 成分 | シタロプラム |
| 効果 | うつ病、社会不安障害などの改善 |
| 副作用 | めまい、倦怠感、動悸、口喝、排尿障害など |
| 飲み方 | 1日1回、10~20mgを夕食後に服用 |
| 製造元 | アクタビス |
| 在庫 | 現在【40mg】欠品中です。次回入荷時期未定。 類似商品は以下をご覧ください。 ・レクサプロ・ジェネリック:エスシタロプラムシュウ酸塩を主成分とするうつ病や社交不安障害の治療薬。 |
| 商品名 | フルニル |
|---|---|
| 成分 | 塩酸フルオキセチン |
| 効果 | うつ病改善 |
| 副作用 | 睡眠障害、頭痛、動悸、便秘、発疹など |
| 飲み方 | 1日1回、20mg~80㎎までを朝食後に服用 |
| 製造元 | インタスファーマ |
| 商品名 | フルオキセチン |
|---|---|
| 成分 | フルオキセチン塩酸塩 |
| 効果 | うつ病や依存症、摂食障害など |
| 副作用 | 吐き気、口の乾燥、不眠症、発汗、食欲の低下、性欲減退や勃起障害など |
| 飲み方 | 1日1回、20mg~80㎎までを朝食後に服用 |
| 製造元 | Adeka |
| 商品名 | アナフラニール・ジェネリック |
|---|---|
| 成分 | クロミプラミン |
| 効果 | うつ病、遺尿症改善 |
| 副作用 | 循環器障害、抗コリン作用、精神神経障害、発疹、肝臓機能障害など |
| 飲み方 | うつ病の場合、1日50~100mgを初期用量で1~3回に分けて服用(最大225mg) 遺尿症の場合、1日20~50mgを1~2回に分けて服用 |
| 製造元 | Consern Pharma,Sun Pharma |
| 商品名 | セルティマ |
|---|---|
| 成分 | 塩酸セルトラリン |
| 効果 | うつ病、パニック障害、不安障害などの改善 |
| 副作用 | 睡眠障害、頭痛、動悸、便秘、発疹など |
| 飲み方 | 1日1回25~100mgを夕食後に服用 |
| 製造元 | インタスファーマ |
| 商品名 | パキシル |
|---|---|
| 成分 | パロキセチン塩酸塩水和物 |
| 効果 | うつ病、パニック障害、強迫性障害などの改善 |
| 副作用 | 目まいや吐き気、傾眠など |
| 飲み方 | 1回10mg~20mgより開始し、1週ごとに10mgずつ増量。飲み方、上限摂取量は症状によって異なる。 |
| 製造元 | GSKファーマ |
| パッケージ | 発送時期により、メーカーパッケージが異なります。 |
| 商品名 | セディール |
|---|---|
| 成分 | タンドスピロン |
| 効果 | 不安障害、睡眠障害、うつ病などの改善 |
| 副作用 | 眠気、ふらつき、倦怠感、認知機能低下、肝機能障害など |
| 飲み方 | 1日30mgを1日3回に分けて服用 |
| 製造元 | 住友ファーマ |
| 商品名 | トラゾドン |
|---|---|
| 成分 | トラゾドン |
| 効果 | うつ病改善 |
| 副作用 | 低血圧、動悸、眠気、めまい、頭痛など |
| 飲み方 | 1日75~100mgを初期用量として服用し、その後200mgまで増量し1日数回に分けて服用 |
| 製造元 | サンファーマ |
| 商品名 | イフェクサーXR |
|---|---|
| 成分 | ベンラファキシン塩酸塩 |
| 効果 | うつ病改善 |
| 副作用 | 傾眠、悪心、動悸、肝機能検査値異常、γ-GTPの上昇など |
| 飲み方 | 1日1回食後に服用。1回37.5mgより開始し、1日225mgまで増量可 |
| 製造元 | ファイザー |
| 在庫 | 現在欠品中です。次回10月中旬入荷予定。 類似商品は以下をご覧ください。 ・イフェクサー・ジェネリック:イフェクサーのジェネリック医薬品で黄色のカプセルが特徴です。 |
| 商品名 | レクサプロ・ジェネリック |
|---|---|
| 成分 | エスシタロプラムシュウ酸塩 |
| 効果 | うつ病、あがり症(社会不安障害)などの改善 |
| 副作用 | めまい、倦怠感、動悸、口喝、排尿障害など |
| 飲み方 | 1日1回、10~20mgを夕食後に服用 |
| 製造元 | シプラ |
| 在庫 | 現在欠品中です。入荷時期未定。 類似標品は以下をご覧ください。 ・シタロプラム シタロプラム配合の抗不安薬です。 |
| 商品名 | エチラーム |
|---|---|
| 成分 | エチゾラム |
| 効果 | 不安障害、心身症、睡眠障害などの緩和 |
| 副作用 | 眠気、ふらつき、脱力感、倦怠感など |
| 飲み方 | 睡眠薬としては1回1錠0.5mgを就寝直前に、抗不安薬としては1日1~3mgを3回に分けて服用 |
| 製造元 | インタスファーマ |
| 在庫 | 薬機法により輸入禁止対象となりました。 |
| 商品名 | ノリトレン・ジェネリック |
|---|---|
| 成分 | 塩酸ノルトリプチリン |
| 効果 | うつ病改善、禁煙補助 |
| 副作用 | 頭痛、便秘、口の渇き、血圧低下、眠気など |
| 飲み方 | うつ病改善としては1日2~3回10-25mgを服用、禁煙補助としては1日25mgを3ヶ月程度まで服用 |
| 製造元 | サンファーマ |
| 在庫 | 現在欠品中です。次回入荷時期未定。 類似商品は以下をご覧ください。 ・ジェイゾロフト:うつ病や不安障害の治療薬 ・レクサプロ・ジェネリック:うつ病や社交不安障害の治療薬 |
| 商品名 | エチゾラム錠 |
|---|---|
| 成分 | エチゾラム |
| 効果 | 不安障害、心身症、睡眠障害などの緩和 |
| 副作用 | 眠気、ふらつき、脱力感、倦怠感など |
| 飲み方 | 睡眠薬としては1~3mgを就寝直前に、抗不安薬としては1.5~3mgを3回に分けて服用 |
| 製造元 | 日医工 |
| 在庫 | 薬機法により輸入禁止対象となりました。 |
| 商品名 | レクサプロ |
|---|---|
| 成分 | エスシタロプラム |
| 効果 | うつ病、社会不安障害などの改善 |
| 副作用 | 悪心、頭痛、かわき、めまい、倦怠感など |
| 飲み方 | 夕食後、1日1回1錠を水またはぬるま湯で服用 |
| 製造元 | ルンドベック |
| 在庫 | 現在欠品中です。入荷時期未定 類似商品は以下をご覧ください。 ・バスピン 不安障害、心身症、睡眠障害などの緩和 ・レクサプロ・ジェネリック うつ病、あがり症(社会不安障害)などの改善 |
| 商品名 | レメロン・ジェネリック |
|---|---|
| 成分 | ミルタザピン |
| 効果 | うつ病改善 |
| 副作用 | 体重増加、けん怠感、胸痛、疲労、精神神経障害など |
| 飲み方 | 1日15mgを初期用量として服用し、その後15~30mgを1日1回服用 |
| 製造元 | Gensenta |
| 在庫 | 現在欠品中です。【15mg】3月下旬入荷予定。 |
| 商品名 | エスシタロプラム |
|---|---|
| 成分 | エスシタロプラムシュウ酸塩 |
| 効果 | うつ病、社会不安障害などの改善 |
| 副作用 | めまい、倦怠感、動悸、口喝、排尿障害など |
| 飲み方 | 1日1回10~20mgを夕食後に服用 |
| 製造元 | アブディイブラヒム |
| 在庫 | 現在欠品中です。 【10mg】26年2月上旬入荷予定。 【20mg】2月下旬入荷予定。 類似商品は以下をご覧ください。 ・レクサプロ・ジェネリック:シプラ社が開発した、うつ病や社交不安障害の治療薬。 |
| 商品名 | オーロリクス |
|---|---|
| 成分 | モクロベミド |
| 効果 | うつ病、不安障害などの改善 |
| 副作用 | 睡眠障害、めまい、吐き気、頭痛など |
| 飲み方 | 食後に1日2回、1錠ずつ服用 |
| 製造元 | Deva |
| 在庫 | 現在欠品中です。 【150mg】次回入荷時期未定。 【300mg】4月中旬入荷予定。 類似商品は以下をご覧ください。 ・シタロプラム:シタロプラム配合のうつ病や不安障害の治療薬。 |
| 商品名 | サインバルタ |
|---|---|
| 成分 | デュロキセチン塩酸塩 |
| 効果 | うつ病改善 |
| 副作用 | 倦怠感、頭痛、動悸、耳鳴、排尿困難など |
| 飲み方 | 1日1回、20mg~60㎎を朝食後に服用 |
| 製造元 | イーライリリー |
| お知らせ | 取り扱い終了商品です。 類似商品は以下をご覧ください。 ・デュゼラ:SNRIに分類する抗うつ剤。デュロキセチン塩酸塩が成分です。 |
| 商品名 | フルボキサミン(ルボックス) |
|---|---|
| 成分 | フルボキサミンマレイン酸塩 |
| 効果 | うつ病、強迫性障害、不安障害などの改善 |
| 副作用 | めまい、動悸、発疹、貧血、口喝など |
| 飲み方 | 毎日決まった時間に、1日50~150mgを2回に分けて食後に服用 |
| 製造元 | アッヴィ |
| 在庫 | 現在欠品中です。次回入荷時期未定。 類似商品は以下をご覧ください。 ・ルボックス・ジェネリック:ファベリンはアボット社が開発した、うつ病や不安障害の治療薬です。 |
| 商品名 | スルピリド |
|---|---|
| 成分 | スルピリド |
| 効果 | うつ病、統合失調症、胃潰瘍の治療 |
| 副作用 | 不眠、眠気、めまい、口渇、胸やけなど |
| 飲み方 | うつ病:1日150~300mgを数回に分けて服用 統合失調症:1日300~600mgを数回に分けて服用 胃・十二指腸潰瘍:1日150mgを3回に分けて服用 |
| 製造元 | Zentiva Saglik Urunleri |
| 在庫 | 現在欠品中です。類似商品は以下をご覧ください。 次回26年2月下旬入荷予定。 ・ジェイゾロフト:選択的セロトニン再取り込み阻害剤。 |
| 商品名 | デパス |
|---|---|
| 成分 | エチゾラム |
| 効果 | 不安障害、心身症、睡眠障害などの緩和 |
| 副作用 | 眠気、ふらつき、脱力感、倦怠感、頭痛など |
| 飲み方 | 1回1錠1mgを、睡眠薬として服用する場合は就寝前に服用、抗不安薬として服用する場合は1日3回に分けて服用 |
| 製造元 | 田辺三菱製薬 |
| 在庫 | 薬機法により輸入禁止対象となりました。 |

登録時のメールアドレス、パスワードを入力の上、ログインして下さい。
パスワードを忘れた
ログインに失敗しました。
メールアドレス、パスワードにお間違いがないかご確認の上、再度ログインして下さい。
パスワードを忘れた
※メールアドレスに誤りがあります。
登録した際のメールアドレスを入力し送信して下さい。
ログインに戻る
あなたへのお知らせ(メール履歴)を表示するにはログインが必要です。
全体へのお知らせは「お薬なびからのお知らせ」をご確認下さい。
パスワードを忘れた
注文履歴を表示するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた
以下の内容で投稿します。よろしければ「送信する」を押して下さい。
以下の内容で投稿します。よろしければ「送信する」を押して下さい。
| 商品名 | |
|---|---|
| 満足度 | |
| 写真 | |
| ニックネーム | |
| レビュー内容 |
※内容を確認後の掲載となります。
※内容によっては非掲載となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
※紹介コードを記載された場合、掲載はいたしかねますのでご了承ください。
以下の内容で送信します。よろしければ「送信する」を押して下さい。
決済が失敗する場合があります。
まれにカード発行会社の規制により、国をまたいだクレジット決済がエラーとなる場合がございます。
クレジット決済ができない場合には、カード発行会社にご連絡いただき、クレジット決済をしたい旨をお伝えいただくことで決済が可能となる場合がございます。
【ご注意ください】
本来、医薬品のクレジット決済はカード規約で禁止されています。
医薬品である旨を伝えてトラブルになったケースもあるようですので、ご連絡される際には「海外の通販サイトを利用したいので制限を解除して欲しい」という旨だけとお伝え下さい。
請求金額が異なる場合があります。
VISA/MASTER/AMEXのカードは元(げん)決済です。
昨今は外貨の変動幅が大きく、元から円へのエクスチェンジ時に為替差益が発生しており、1~2%前後の手数料が掛かっております。
購入金額以外に、この為替差益がお客様の負担となりクレジット会社から請求される可能性がございます。
ご負担頂いた3%分を当サイトでは、次回購入時に利用頂けるポイントとして付与しております。
こちらをご理解の上で、クレジット決済をお願い致します。
※当サイトでは、銀行振込みをオススメしております。
以下の内容で登録します。よろしければ「登録する」を押して下さい。
| 名前 | |
|---|---|
| フリガナ | |
| メールアドレス | |
| パスワード |